かつて国分寺市にあった戸倉新田を探しに出かけました。
出発は中央線国立駅。このあたり、国分寺市と国立市が入り組んでいる地形で、ややこしいのです。
坂道や住宅街を北東の方向にかなり歩いて、戸倉という地域に到着。
このあたりはきちんと区切られた細い道に、こぎれいな新しい住宅が並んでいました。
この道路の区切り方は、かつては新田の畑だったところの名残りかもしれません。
すると道路の突き当たりに、何の樹木か分かりませんが、フェンスのように植えられているのが見えました。
果樹園のようでした。
そしてその隣に、目指していた満福寺というお寺の墓地が見えました。
お寺の周囲をぐるりと廻ると、今度は赤い塀が続き、そこが戸倉神社でした。
かなり立派な神社でした。
木に隠れて見えづらいのですが、「この神社は享保年間にあきる野市戸倉にある三島神社の分霊であり、山王大権現と称して、戸倉新田の鎮守とした」という由来が書かれていました。あきる野からやってきたのですね。その後、明治2年になって、戸倉神社と名前を変えたそうです。
鳥居をくぐりました。
境内にある社殿の様子。
「鎮座250年記念」と書かれた碑にも、神社のいわれが刻まれていました。
私が映り込んでいます。
この神社は1722年、享保の時代に、「新田を作るように」という高札が日本橋に建てられて、それを見て、あきる野檜原村からから新田開発にやってきた鄕左衛門という人たちの遺産なのでした。ちなみに檜原村は、現在、東京都でたった一つの村なんだそうです。
その後、1760年(宝暦10年)までには42軒の移住者があり、そのうちの半数が檜原村出身者だったそうです。(国分寺市史)
そして鄕左衛門の出身地であった戸倉村の神社を、分社しました。
またその後、檜原村から満福寺を神社の東に設置しました。
「国分寺市有形文化財調査報告書(神社・寺院)」より
国立駅から熱い日差しを浴びながら、25分も歩いて来て良かったと思いました。
そして神社やお寺の周囲を歩いて見ると、素晴らしい証拠を見つけました。
こちらの石碑です。
脇には「武州多摩郡 戸倉新田村」という文字が刻まれていました。
これまで新田に関する書物や論文はいくつも目を通していましたが、平右衛門さんの慰労塔や感謝塔などはあっても、実際に新田の文字が刻まれたものは初めてでした。やはり自分で歩いて見ると、こんな発見もあるのだと思いました。
その周囲の場所は、とても立派な豪農のような方のお宅でした。そして正面には満福寺が立っていました。
昔は神社とお寺がセットのように並んでいたのですね。
あたりはこぎれいな現代風の住宅が並んでいましたが、この一画だけは農家の雰囲気があり、果樹園のようなところでした。先代が開発した農地を大事に守っているように見えました。
ブルーベリーのもぎ取りもできるそうです。
農園は、国分寺市の支援を受けているという看板がありました。
国分寺市の支援はこちらのホームページにも書かれていました。
https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/faq/kurashi/1005241/1005306/1006353.html
道路の反対側には、お菓子のお店・シャトレーゼがあったので、そこで休憩しようと思いましたが、そこはケーキやお菓子の販売だけで、座席はなくて残念。
仕方なく国立駅までシルバーパスで戻りました。
そして駅前のコメダで、こちらのかき氷を注文。今年初でしょうか。
かなりボリュームがあり、お昼ご飯代わりになりました。
この日の国分寺歩きは、いろいろと収穫がありました。
こちらは戸倉新田があったと思われる場所の地図です。細かい道路は、新田(畑)の跡のように見えました。
通りの名前も「戸倉通り」だったので、よほど戸倉の影響が大きかったのでしょうね。
.JPG)









.JPG)











.JPG)
.JPG)


.JPG)


.JPG)

.JPG)


%20(1)%20(1).JPG)


-EDIT.jpg)

.JPG)


.JPG)
.JPG)
.JPG)








-EFFECTS.jpg)

%20(1).JPG)
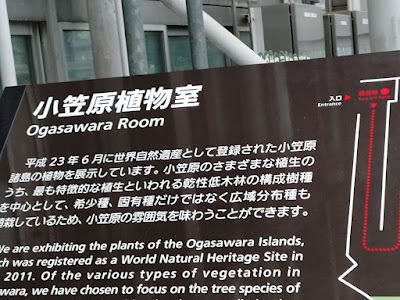


.JPG)



