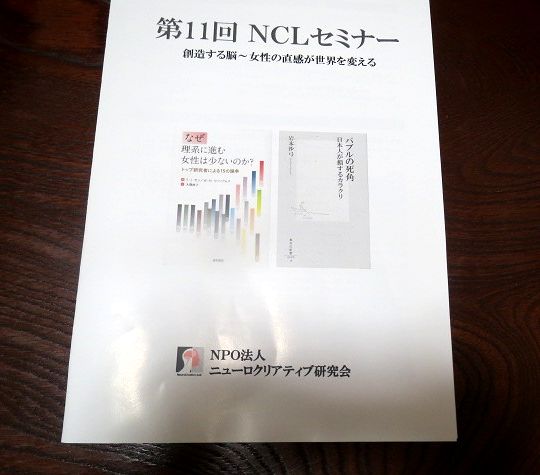ピカソの絵ですが、上下、逆向きですね。
実は、これが絵が上手に描ける秘密なのです。
*******
私はごく小さな頃、家でよく「お絵かき」をして遊んでいた記憶がありました。
それも同じような女の子の絵ばかり描いていました。
少女漫画の主人公のような絵だったと思いますが、そこそこうまく描けていたような思い出があります。
それが小学校高学年になった時、図工は専科の先生が教えることになりました。
一緒のクラスに、とても観察力に優れて、細かい絵を描く男子生徒がいて、その子は、いつも図工の先生に褒められていました。
私にはとうてい描けないような丁寧な絵でした。
それ以来、そういう絵を描くのは自分には無理だと思い、絵を描く興味が失せてしまったようです。
小学校、中学校は図工の時間はなんとか普通に過ごしていましたが、高校の芸術科目は選択制ということになり、美術は取りませんでした。
ということで、私の長い歴史の中では、絵は見るものであって、自分で描くものではなくなりました。
******
前置きが長くなりましたが、そんなこんなで、ご近所で絵を教えているという方の展覧会に行った時にも、絵手紙の先生の展覧会に行った時も、「教室があるから一緒に絵を描きましょう。是非いらして下さい」というお誘いがありました。
でも、自分は絵が描けないからダメだという意識があるので、絵の教室には行っても無駄だろうと思っていました。
絵を描くということに対するコンプレックスがあったのでしょうね。
そんなとき、脳科学セミナーのお知らせで、「あなたも絵が描けるようになる」という方法を教えていただけるワークショップがあることを知りました。
普通の絵画教室ではないようなので、ちょっと覗いて見ることにしました。
この会は、眼鏡のパリ-ミキがスポンサーとなって、脳科学者の先生たちと共同で行っているニューロクリアティブ研究会という研究会です。
会社の入り口では、眼鏡をかけたキティちゃんがお出迎えをしていました。
今回は20人ほどの方が参加されていましたが、会場にはクリスマスツリーなどが飾られていて、和やかな雰囲気でした。
まず、脳科学の専門家である理研の入來篤史先生から「人間と脳と芸術」というお話を伺いました。
動物は感覚と反応で生きているのに対して、人間は言語という象徴を用いていること。
また芸術とは美の追求であること、などの前置きがありました。
そして、動物の段階では脳が発達していないので、ただ食べるだけ、生きるだけという本能的生活ですが、だんだん進化して、脳が大きくなるとともに、それ以外にも生きる目的が生まれてくるとのこと。
また人類も、石器時代より脳の重さが増してきて、道具を使ったりしてするようになったという話を聞きました。
その後は、専門用語でのちょいと難しいお話になったので、ここではまとめきれませんが、30分くらいのレクチャーでした。
実は入來先生の講演は、10年ほど前の2007年に「脳と教育」というテーマでお聞きしていた▼ことがありました。
その時の、お若い頃にされていたという剣道のりりしいお姿が印象的でした。
当時の講演でもサルの実験のビデオを見せていただきましたが、今回もサルが道具を使って学習していく様子を見せていただきました。
ワークショップを担当されたのは、「アート&ブレイン」▼という会を主宰されている斎藤由江先生です。
アメリカの大学で学んだという、変わった方法で絵を教えていらっしゃいます。
3歳の子供から85歳の老人まで、その方法で絵を描くと、みんなとても絵が上達するとのことでした。
私たちが実際に行ったのは、次の3つのパターンです。
1.絵を上下逆さまに置いて、その状態の絵を反対側の空きスペースに写し取る。
30分かけて、じっくりと描く。
↓
その結果はこちら。
(本来の方向に置き直したものです)
逆さまなので、何が何だかよく分からず、結果的にじっくりと絵を見て描いたからでしょうか、普通に描いた時よりも、うまく描けたかも?
2.右手と左手を180度の位置に置いて、鉛筆を持った手と反対側の手をじっと眺めながら、紙を見ないで、1ミリ進むのに1秒かけてじっくりと手の輪郭を描く。
この方は2回繰り返す。それぞれ5分ずつ描きました。
2回目は袖の布の様子を描いたつもりです。
これは「アイハンドコーディネーション」と呼ばれていて、目の動きと手の動きを一つにする方法だそうで、とても難しかったですね。
何がなんだか分からない絵になりました。
それでも上の最初の方よりも、下の2回目の方がスムーズに描けていました。
3.「ビューファインダー」という透けたアクリル板のようなものに、手を下から当てて、その輪郭やシワなどをじっくりと描く。その後、ファインダーからはずして、同じ絵を描く。
↓
作業中はこんな感じです。
シワシワな手ですいませんが、リアルに描くとこうなります。
そして手を枠から離してみると、こんなふうに描いていたのですね。
なかなか立体的に描けているようです。
この後は、ファインダーに描いたものを、こんどは紙に写し取るという作業がありました。
(写真はありません)
1.2.3のそれぞれの作業をした後は、壁にみんなの作品を飾って、先生の講評があり、また描いた本人が感想などを述べました。
それぞれみなさん、個性が出ていて、とても面白かったです。
私の個人的な感想としては、とにかくこういう体験はしたことがなかったので、かなり疲れました。
とくに2の、首と手を180度の方向に置くというのは、首が痛くなって、早くやめたいと思うほどでした。
またどの方法も、私はよほどせっかちなのか、時間が余ってしまいました。
いくらじっくりと描いても、他の方よりも早かったようです。
でも、それが絵がうまく描けないことの理由だったのかもしれません。
観察力が足りなかったのでしょうね。
斎藤先生のお話では、「絵を描くときは右脳で描く」「ゆっくりと描く」「自分が勝手に見て描いている脳のクセを直して、本来の空間を取り戻す」というようなことが大切だということでした。
本当は、もっと時間をかけて作業を行うのだそうですが、なかなか刺激的なワークショップでした。
ただしこれで私に絵を描くという才能が開花したかどうかは分かりませんが。
お二人の先生、ニューロクリアティブ研究会のみなさまに、お礼申し上げます。