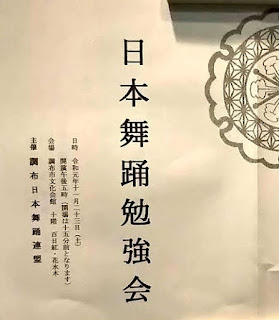以前、市民カレッジで日舞を習ったお仲間のY子さんや、その時に助手をされていたMさんもご一緒でした。
S子さんはあぜくら会の会員なので、チケットは事前にお安く予約してくださいました。
いつもありがとうございます。
ロビーを上から見た様子です。
受付には黒留袖の名取さん(?)や、きれいな色の着物の方がたくさん並んでいらっしゃいました。
さて、これから舞台が始まります。
「京舞」は京都・祇園の世界の踊りですが、18世紀末頃から伝わっているそうです。
その京都の踊りが、東京では21年ぶりに公演されるとのことでした。
オープニングは「京の四季」。
総勢50人くらいの華やかな踊りでした。
ほんとにきれいでしたね。
その後は能楽「羽衣」に由来した踊りや、源氏物語の「葵上」を元にした「梓」という地唄などがありました。
休憩時間には2階の展示場で、華やかな衣装を拝見。
どれも実際に舞台で着用されたものだそうです。
そしていよいよ、五世・井上八千代さんが井上安寿子さんとの親子競演で「三つ面椀久」の登場となりました。
これは上方に伝わる「椀久もの」と言われる踊りですが、お面を三種類取り替えて踊るところが、私には珍しかったですね。
なんといっても八千代さんの鍛えられた身体の、ぶれない踊りが素晴らしかったです。片足立ちですくっと立つつところは、バレエのようなお姿でした。
以前、銕仙会の能楽堂で井上流の踊りを見た時▼は、安寿子さんだけの踊りで若々しくて素敵でしたが、今回の舞はさすがお家元でと感じました。
この踊りには、女流義太夫・竹本駒之助さんの義太夫があり、語りのお声に圧倒されました。
そして次の場面で、さっと幕が開くと、舞台には私の三味線の先生が登場されたので、びっくりしました。
後で伺うと、この日は予定されていた三味線奏者のご都合により、急遽、代役で出演されたのだそうです。
でもいつもと変わらない美しいお姿で、きちっと演奏されていて、素敵でした。
先生のお仲間のお唄の方たちの声も会場にピーンと鳴り響き、私は踊りよりも地方の方ばかり眺めていました。
締めくくりは「手打」といって、大勢の芸妓さんが拍子木を打つ「廓の賑」で、気分も高揚して、気持ちよく終了しました。
ご一緒した皆さん方と、歌舞伎役者の絵画の前で撮影。
「藤娘」を背景にして。
やはり友人たちの無地っぽい着物は、会場の雰囲気に合っていますね。
こちらは羽左衛門の絵画でした。
この日は会場が大入り満員のため、終了後には友人たちと離れ離れになってしまい、ゆっくりできなかったのは残念でしたが、美しい舞の世界にどっぷりと浸かれたし、三味線の先生の演奏も聞けたので、満足でした。
シルバーパスを使って、新宿まで都バスで帰りました。
******
この日の装い。
こういうときにはやはり柔らかものを着た方が良いと思い、紫の飛び小紋にしました。
いつもはお手軽な紬着物が多いので、たまに柔らかものにすると、着付けに手間取りますね。
「銀座ぽわる」の福袋(「30代向け」と書かれていた!)で求めたものです。
袋帯もめったにしないのですが、たまには締めないと。
こちらの淡い色の道中着は、婿さんのお母様の手縫いです。