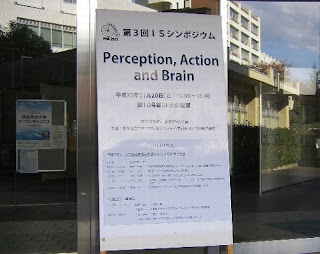「ビロード」と聞いて、みなさんはどんなものを想像されますか?
ビロードというのは今から400年ほど前の天文年間にポルトガルより伝来したものだそうですが、ビロードというと、ショールとか下駄の鼻緒、重みのあるカーテンなどを思い浮かべるのではないかしら?
ところがそんな決まり切った想像を見事に裏切られたのが、長浜で見学した「タケツネ」のビロードだったのです。
それはまさに天鵞絨(てんがじゅう)という名にふさわしい、ソフトで上品で光沢があり、そして美しい絵柄の入った夢のような生地だったのです。
********
長浜駅を降りて、「タケツネ」に電話をしました。
この会社にはインターネットを通じて、会社見学を希望していることを伝えていたのですが、会社の方がわざわざ駅まで車で迎えに来て下さいました。
そして到着したのがこちらの会社です。

この会社は大正8年創業のビロード専門の織物会社ですが、輪奈(わな)ビロードという特殊なビロードを作っています。
「輪奈」というのは「パイル」という意味だそうで、昔は胴線を使用していたそうですが、現在では改良を重ねて「ポリエチレンモノフィラメント」という材料を布地に織り込んでいるのです。
こちらの写真がその「輪奈」の原料で、緑・紺・赤の三色があり、色によってその太さが違っているそうです。


こちらの写真の上の方が、現在の材料を織り込んだもの。
ループ状になっていますよね。それが特徴なんだそうです。
下の方が胴線を織り込んだものですが、これは一本一本手で抜き取っていたそうです。

お隣にある工場で、この針金を「紋紙」を使って織るそうです。
そして織り上がったこの布地を今度は「紋切」(もんきり)といって、特殊な小刀で絵の部分だけを切り取るのです。

気の遠くなるような作業をされていました。
反物というのはコート用は長さが11.5メートル、着物用は長さが13メートルあるので、その作業をずっと繰り返すのですね。
写真にある虫眼鏡で覗いてみましたが、きれいに絵が切り取られていました。

このようにパイルをカットするので、ふわふわの状態のなるのだとか。
この布地を今度は水に漬けてそして乾燥をして、その後、この線を抜くのだそうです。
そして白い生地にしてから色を染めて、検査をしてようやく製品になるのです。
ものすごく手がかかっていますね。いったい何工程あるのでしょうか。
できあがった製品を触らせていただきましたが、とても柔らかく、おまけに軽く、そして空気を含んでいるので着ているととても暖かいので、究極のコートになるんだそうです。
それというのもこのビロードは絹100パーセントでできているので、レーヨンなどが入ったものとは違うのでしょうね。

このような製造過程の説明をしていただいたのちには、お茶とお菓子までご馳走になってしまいました。
こちらの会社では80歳くらいの美しい女性社長ともお会いできましたが、
「伝統を守っているだけではだめなの。新しいものを取り入れていかないとね」とお話しされていたのが印象的でした。
今年の年末には池袋の東武デパートの職人展でこちらの会社の製品も出店するそうなので、是非行ってみようと思います。本当に素晴らしい職人技を間近で拝見させていただいて、ありがとうございました。

「タケツネ」には着物には詳しい京都のさとさんも一緒に行きましたが、二人して「いいものを見せていただいてよかったわね」と感激して、会社を後にしたのでした。
タケツネ▼さとさんのブログ▼