またまたブログの投稿間隔が空いてしまいました。
その原因の一つはWindows11アップデートに関わるトラブルでした。おまけにWi-Fiのトラブルも重なり、踏まれたり蹴られたり状態が続きました。
おまけにその後はコンクリートの地面に顔面から突っ込む、というドジをやらかしてしまいました。
一応なんとか修復(?)しつつありますが、眼鏡もブーツもパーになりました。それでも私の身代わりになってくれたと思い、とりあえずブーツは新調しました。眼鏡はとりあえず手持ちのもので、なんとかやりくりしています。
そういうトホホな日々が続いておりました。
******
さて、11月9日には、文京区千駄木にある「旧安田楠雄邸庭園」で石川県七尾市からやってきた「花嫁のれん」という展覧会に出かけました。
「きもの倶楽部」の皆さんとご一緒でした。
メトロ千代田線の千駄木駅で待ち合わせて、駅から坂道を上り、静かな住宅街のお屋敷へ。
同行者さんたちの後ろ姿を隠し撮り。
さてお屋敷に到着。
このお屋敷は「日本ナショナルトラスト」という日本の優れた文化財や自然の風景を保全して活用する活動をしているグループの保護対象になっています。
こちらは大正8年(1919年)に建てられたそうですが、関東大震災や戦災からものがれ、古き良き時代を保ったお屋敷でした。安田善四郎という豊島園の創業者が住まわれていたところです。
お屋敷の中には、防空壕に続く抜け道があったり、昔の磨りガラスが使われていたり、ゴブラン織の応接セットがあったり。。。。と、まるでドラマの世界のようでした。
(写真はカタログより)
花嫁さんが結婚するにあたって、実家で準備した大きなのれんを、嫁ぎ先の仏間の前にかけ、のれんを分けて中に入り、「こちらの家の嫁になり、実家には戻りません」と宣言するのだそうです。のれんといっても、サイズがベッドカバーほどあり、とても立派なものでした。
友禅染めののれんは美しく、ため息が出るほどでした。そしてどののれんにも、それぞれの物語があることが説明されていました。
面白いことに、男性が婿入りするときに用意するという「男のれん」もありました。色は青や緑などの色を使っていました。(こちらは撮影可)
美しいパンフレットもいただきましたが、こののれん、お値段はもちろん非公開ですが、いったいいくらほどするのでしょうね。著名な絵師に依頼するのであれば、非常に高価でしょう。世界に一つの手描きなのですから。
ところでこちらに伺った翌日、たまたまテレビを見ていたら、NHK「首都圏ニュース」でこの展示会が取り上げられていました。
会場は撮影禁止でしたので、テレビ画面で見た豪華なのれんをちょっとご紹介します。
いわゆるのれんのイメージよりも、ずっと大きなのれんです。
今回は能登の復興を支援するために、東京で開催されました。
七尾市では、商店街のおかみさん達が、町を元気にするために、平成16年からのれん展をスタートさせました。
地元の「一本杉通り」では明治から平成までののれんを見ることができるそうです。
お屋敷の前でみなさんと写真撮影。
(写真は「きもの倶楽部」ぶちょーさん提供)
それにしても能登の婚礼文化は、古き良き歴史を保ってすばらしいとは思いましたが、お金がかかりそうですね。「仏間」のあるおうち、北陸では普通のことなのでしょうか? 少なくともマンション暮らしの家では、現実離れで、映画の世界のように感じました。これは庶民のひがみかもしれませんが・・・
この後、千駄木を散策しましたが、それはまた別のブログで。

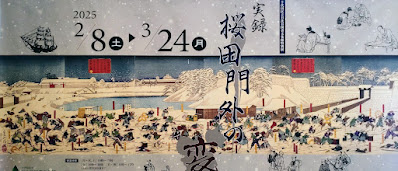
%20(1).JPG)





%20(2).JPG)



.JPG)
.JPG)
.JPG)
%20(1).JPG)

.JPG)

.JPG)


.JPG)


.JPG)



.JPG)












%20(1).JPG)
%20(1).JPG)
.JPG)











